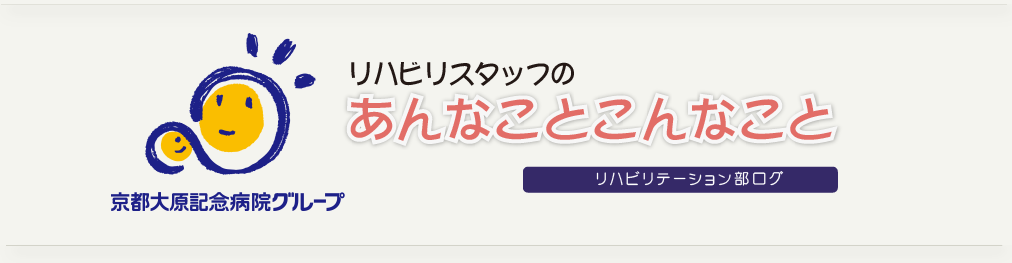![]()
更に小ネタ
2024年3月01日(金)
今朝出がけにまずないとは思いましたが念のため嫁さんに聞いてみました。
「大谷の相手ってあんたか?」
違うそうです。
106333 20240301 1140
106444 20240306 1130
![]()
小ネタ
2024年2月05日(月)
本日ある病棟で火災訓練をやっているところに行きあいました。
胸に「患者」のゼッケンをつけた看護師が車椅子で搬送されていました。
私も随分前に火災訓練で患者役をしたことがあります。
設定では火元病室の見守りで移動可能な患者という役で、職員が迎えに来るまで病室待機となっていました。
結果私という「患者」は焼死しました。
訓練用の火災報知機が鳴る前から胸に「患者」のゼッケンをつけて待機していたんですが、館内放送が「訓練終了」とアナウンスする迄、火元病室に捨て置かれたままで「笑止焼死」という結果になりました。
訓練でよかったです。
105849 20240205 1650
105877 20240206 1645
105952 20240209 1720
![]()
口笛
2024年2月01日(木)
またも話題は45年前高校1年の9月。
7月に骨折した左下腿のギプスが1か月ぶりにとれて、学校に戻る道すがら(授業の途中で抜け出して受診に行きました)、口笛を吹こうとしました。
鳴らない。何度口笛を吹こうとしても鳴らない。
変だなとは思いつつもその時はそれで終わったんです。
夕食時何故か口に入れた食物が右側に寄って行く。
変だなと思いつつも食事を終えて、入浴して頭を洗っているとやたらと右目が滲みる。
頭を漱いで、鏡で顔を見てみると顔の右半分が動いていないorz
その時は顔面麻痺が治るまで3週間ほどかかりました。
昨年末の日曜日いつも通りいつもの川の土手ををウォーキングしていて、昼間なのに珍しく人影もなく気持ちのいい日だったので口笛を吹こうとしたら音が出ない。
ギョッとして慌てて顔に触ってみたけど顔は動いてるように思える。
スマホで顔を確認したけど麻痺はしていない。
でも口笛は出ない。
両手で顔を挟んでもう少し口周囲に皮膚全体を寄せるとかすかに音が出る。
衰えってこんなとこにも出るのかと衝撃でした。
という話をある医師にしたら
「俺も」
「え゛?」
「(口笛が)出ない」
とりあえず私は言語聴覚士に自主トレ用のメニューを作ってもらい、リハビリに励むことにします。
105756 20240201 1630
105780 20240202 1630
![]()
ダイバーシティ
2023年3月14日(火)
巷間よく目にしたり耳にしたりしますが、どういう意味だろうと調べてみたら「多様性」だそうです。わかった瞬間「日本語で言えよ」と思った私は古いんでしょうか。
「偏見をなくし多様性を受け入れましょう」の意で「ダイバーシティ」という言葉が使われているらしいです。
ヒポクラテスは「自由人と奴隷の別なく」、ナイチンゲールは「敵、味方の別なく」と医の偉人は患者には均しく接せよと言うことによって、皆平等と言いたかったのでしょう。
先達に倣い、医療人はまずそうあるべきということでしょうか。
偉人を引き合いに出しましたが、凡人の悲しさ、私自身はいろいろと偏見の持ち主だろうなと考えています。
「だろうな」とは自覚していないからこその「偏見」だと思うからです。
でも自覚すればOK(偏見解消)ではなく、自覚しなければ偏見の解消に至る思考も生まれないと考えています。
30数年前厚生省主催の研修会に参加した時、講師の一人である臨床心理士は「同性愛は治りません」と言い放ちました。
「治らない」という以上、LGBTなどに代表されるsexualminorityの人たちは「病気」と考えられていたわけです。今となっては大問題ですが当時はそう考えていた人は少なくなかったと思います。
先日はLGBT関連の発言で首相秘書官の首が飛びました。なんでも隣人にLGBTの人がいると思うだけで気持ち悪いと言ったとか。
誤解を恐れず言うなら「私」もそうでした。
ただsexualminorityといっても、以前は性的指向と性自認の二つの大きな視点があるとも知らず、LGBTのBやTのことなど何も知らず、LやGについての知識が少々あるだけでした(だから偏見があるともいえる)。
とにかくsexualminorityは病気じゃない、異常でもない、多様性の表れと言われるようになってきたので、数年前になりますがこのままではまずいぞと自分自身の考えの見直しを試みました。
私自身の場合、sexualminorityすべてを知っているわけではありませんでしたが、あらためて考えてみると気持ち悪いと感じているのは「G」だけと気付きました。他はなんともないというか関心がないというか。
何故かなと考えていくと答えは簡単で男に言い寄られると嫌だから。
そこまで考えていくと「誰でもそうじゃん」と。
この「誰でもそうじゃん」は男に言い寄られたらではなくて「誰でも意に沿わない相手に言い寄られたら」ということです。
相手が男だろうが女だろうが好きでもない相手に言い寄られたら気持ち悪いとまではいかなくとも、困惑するでしょう。その上グイグイ来られたら誰でも困惑より嫌悪や恐怖になるはずです。
そうでない限りは誰がどんな好みだろうが、誰が好きだろうが一向にお構いなしだと気付きました(私の場合はですが)。私が木村文乃のファンであっても誰にもとやかく言われないように。
ここでの私の偏見は男の同性愛者は無条件に私に言い寄ってくるかもしれないという思いこみというか、決めつけでした。冷静に考えればそんなはずはありません。相手にだって選ぶ権利はあります。
よし、これで私の偏見の一つは解消された、とはなりませんでした。
sexualminorityのうちある人たちだけどうしても「病気」としか思えなく、結局そこを「病気」としか思えないなら偏見が解消されたとは言えないからです。
「彼ら」を病気としか考えられず、病気でないならsexualminority全体がやっぱり「異常」ということになると、私自身の偏見が解消されないと呻吟したのですが、何の糸口もつかめない。
sexualminorityに偏見がないと公言する何人かに「彼ら」の話題を振ってみたことがあるのですが、全員異口同音に「あんな病気の連中は!」と怒気交じりの反応が返ってきました。「偏見がない」と言い切る人がここまで言うからには偏見ではなくて本当に病気なのかもと一瞬思いましたが、理由はわからないけどそんなわけはない。
私の言う「彼ら」とは小児性愛者、所謂ロリコンです。
病院のブログで何書いてんだと思われるでしょうが、もう少しお付き合いください。
「彼ら」もsexualminorityには違いありません。にもかかわらず何故「病気」としか思えないのか。
今から思えば随分と簡単なことなんですが「偏見」に凝り固まると簡単なことさえ分からなくなります。
いつ迄も「病気」「病気でない」と堂々巡りで行き詰まっているので何気にネットに何かないかなとサーフィンしていたら、ある人が「彼ら」のことを「彼らも気の毒だ」と書いてる記事に行き当たりました。
通常性的志向におけるsexualminorityはminorityと言えども必ず同じ志向の相手が少ないながらもどこかにいてその欲求を満たすことが可能です。ですが「彼ら」にはそれができない。同じ志向の「仲間」はいても「相手」はいません。それどころか「相手」の写真一枚持つことさえ違法です。「気の毒」とはそういうことです。
あぁなるほど。
私をはじめ「彼ら」を「病気」とみなしていた人は必ず子供にいたずらすると決めつけていたからです。勿論大多数の人は苦しみながらも法に則った生活を送っているでしょう。触法者は一部にしか過ぎないはずです。
それに子供にいたずらするのは「病気」ではなく「犯罪」です。
それだけのことが「偏見」を持っているとわからなくなるわけです。
文章でさらっと書きましたが、自分自身に偏見があると思ってから、ここに至るまでに5年ほどかかっています。
「人間皆平等やし」「おぉそうか」で済む話ではなくて、単純に物事を知るのではなく、理解しなければならないのに「偏見」が邪魔するので時間がかかりました。
とりあえず私の中のたくさんある偏見の一つはこれで解消できたでしょうか。
医の先達の遺訓に少しは添えたでしょうか。
凡人ゆえに言い切れないところが残念です。
99817 20230314 1050
99860 20230315 1015
99978 20230320 1600
100000 20230323 0900
100027 20230324 1135
![]()
知らなんだ
2022年12月20日(火)
この時期学卒就職希望者の面接なんかが予定に入ってきます。
「内定!」と言うことになれば、来年度の就職予定者リストに私が入力することになります。
提出された履歴書をもとに入力するわけですが、毎度混乱するのが生年月日。
人によって西暦だったり元号表記だったりで、内定者がストレートの学卒新人だけなら今年は誰もが平成12年~平成14年(2000年~2002年)生まれで記入しやすいのですが、一浪(二、三、四…)も居れば一留(二、三、四…)も居る。浪人と言っても国試浪人もいる。かと思えば30過ぎの社会人経験者もいる。
で結局その都度西暦と元号を確認する羽目になります。
一々ネットで調べるのも、手帳をめくるのも面倒で年齢早見表を印刷して机に貼っています。
その表を作成するときに気がついたのですが
昭和は昭和64年(AD1989年)1月7日まで。平成は平成元年(AD1989年)1月8日から。
平成は平成31年(AD2019年)4月30日まで。令和は令和元年(AD2019年)5月1日から。
大正は大正15年(AD1926年)12月25日まで。昭和は昭和元年(AD1926年)12月26日からと思いきや12月25日からです。
つまり1926年12月25日は大正でもあり昭和でもあるんです。
実際に私の頭の中には昭和元年は一週間しかなかったというのがあって、昭和の始まりは12月25日と認識してたので、大正は12月24日までと勝手に思い込んでいました(因みに明治→大正も7月30日で日が被る)。
知らなかった…
幾つになっても知らなかったことを知る機会と言うのは、変わらずあるものとわかっちゃいますが、この齢にして自分で知ってるつもりでいて知らなかったと言うか誤解していたことがあるというのは驚きです。
98139 20221220 1050
98172 20221221 1330
98203 20221223 1200
![]()
夕暮れ時
2022年12月07日(水)
随分と間が開いてしまいました。
「自立(その3)」を書いてたらまとまらなくなりました。
今回は話題を変えようと思います。
申し訳ありません <m(__)m>
日が短くなりましたね。
今朝はガレージに向かう途中で日の出を見ましたが、6時51分でした。今日の日の入りは4時45分となっています。
今年の冬至は12月22日だそうですから、これからますます日の出は遅くなって、日の入りは早まることになります。
私が九州からこちらへ出てきて驚いたのは九州と比べて日の出、日の入りが早いことです。九州より関西の方が東に位置していますから、当たり前っちゃぁ当たり前ですが、若い頃は暁を覚えずなんで日の出が何時だろうといつも夢枕でしたが、冬場は夕方5時で真っ暗と言うのは結構な驚きでした。
不思議なもので夜歩くのは何とも思わないのですが、夕方真っ暗だと何となくウォーキングをためらってしまうのはどういう気持ちなんでしょうか。
平日は仕事しているので歩く時間もないのですが、休日なんか十分に明るいようだと歩きに出かけますが、夕方真っ暗だとやめとこう、夕食食べてからにしようと思ってしまいます。
我が事ながらよくわかりません。
97926 20221207 1550
97947 20221208 1345
98021 20221213 1515
![]()
過ぎたるは…
2022年9月27日(火)
以前「規則正しい生活」について書きました。
その時「規則正しい生活」が必要なのは中年以降だと書きましたが、不規則な生活は勿論のこと、下手に生活習慣を変えるのも止めたほうが良いと気が付きました。
今年7月くらいでしたか、オミクロン株が猛威を振るいだしたころ、特別何かをするわけでもなかったんですが、いつもより1時間早めに起きて出勤するようにしました。
当初はやはり眠かったのですが、2週間もすれば慣れてきて、休みの日でもその時間になれば目が覚めるようになりました。とここまでは良かったんですけど。
オミクロンも落ち着いたし、そも早く出勤しても私にできることはないしで、以前の起床時間に戻そうとしたところ、
元に戻らない…
起床時間を早くすることは目覚まし使えばいいわけですが、起床時間を遅らせるのはなかなかに容易ではないということに気がつきました。
起床時間がある程度習慣化すると、いつもより遅く起きようとしても、いつもの時間に目覚めてしまうわけで、習慣化していると二度寝も難しい。
今は早くに目が覚めても強引に6時までは床から離れないようにしていますが、いつ元に戻るのやら。
話は変わりますが、私が利用している万歩計のアプリは1日に2万歩ほど歩くと10~12円ほどのポイントになります。
あるECサイトのアプリを起動していくつかの広告を見れば、毎日5円にはなります。
「早起きは三文の得(徳)」の三文は振れ幅はありますが今の貨幣価値に直すと50~300円にもなるとか。
定期預金金利が0.002%で100万円預けても1年で20円ですから毎日少なくとも50円の得とは有り難い。
ですが、実際1時間早起きしても50円の得より、睡眠不足気味になって50円分の健康上の負債が増したような気がします。
まぁ何事も「過ぎたるは…」と言うことです。
96477 20220927 1630
![]()
敵の名は。
2022年8月12日(金)
コロナ禍になって一人一人の衛生意識はかなり高まったのかなと思います。
私の感染症に対する意識は医療職に就いてから一度変わり、コロナでもう一度変わりました。
その上実家が水商売だっただけに違う面での衛生意識は高かったのかなと。
水商売で衛生上の問題と言うと誰しも「食中毒」が一番に頭に浮かぶかなと思います。
うちは寿司屋でしたからことのほか食中毒には気を付けて、あの寿司屋でお馴染みのネタケース(ガラス張りの陳列棚ですね)と大型冷蔵庫は父親拘りのオーダーメイドでした。
(エアコンではなく)クーラーも家庭であるところはまれ扇風機がデフォ、客商売の店舗にも一部しかまだ無かった時期に既にありました。
店の床は全部タイル張りで、炊事場はいつも井戸水をかけ流し、店内も週に一回は水を流してデッキブラシで磨いていました。
ネタを扱う布巾は洗濯の後煮沸消毒したものを一回一回変えていました。
勿論他にも細々とした対策はかなりやっていました。
こういったことは習慣化したうえで「慣れ」にさえ気を付ければ、まぁ食中毒は防げるものです。
生モノを扱う商売でしたから、やはりネズ公も心配の種でした。ですがこいつらは人の気配がしたり明るいところではなかなか顔をのぞかせないので、お客さんがいる場面で、のそっと出てくる心配はありませんし、生ごみを隔離し、排水溝をはじめとして出入りする穴と言う穴をシャットアウトしたうえに、なおネズミ捕りを定期的に仕掛ければ恐れるに足らずです。
問題は「G」です「G」。
皆さんご存じですか?
「G」は人間の致死量の20倍の放射線(γ線)を浴びてなお「平気」だそうです。
また「G」の頭部を出血しないように切断すると、1週間動き回った挙句最後は「脱水」で死ぬということです。
人類滅亡後も確実に生き残ると言われる所以です。
同じ頭文字を持つ「ゴルゴ13」をも凌ぐ生命力の「G」の侵入をひとたび許せば、そこは「G」にとってはこの上ないほどの楽園。大型冷蔵庫の裏は「G」にとって常夏のリゾート、人の手も目も及ばぬそこかしこに食物が落ちている。奴らが蔓延ればその駆除には数年を要します。
「G」もネズミと一緒で闇夜の跳梁跋扈がお得意ではあるけど、明るいから、人の気配があるから、遠慮するなどと言う奥床しさは欠片もなく、目の端でその姿を捉えること数限りなくorz
奴らの台頭は店の信用にかかわると父も随分と気をもんでいました。
月一回の大掃除とバルサン、細かな食中毒対策で、根絶したかどうかはともかく、その姿を見なくなるようになるまで、数年かかったと思います。
ネズミも「G」も駆除は食中毒対策の一環ですが、仮にそのリスクがないにせよ、その存在自体が人を不快にさせるものですから、夏場ですらその姿をしばらく見ないなとなった時には、ちょっとほっとしたように思います。
とにかく姿どころかその名前を口にすることも文字にすることも不快に思う人間もいるほどで、「G」としか表現しない人も少なからずいるわけですから。
コロナ対策だけでなく、食中毒対策も結構大変だよと言う話でした。
95572 20220812 1440
95589 20220813 1440
95720 20220818 1340
![]()
こういう世界
2022年7月06日(水)
先日の夜いつも通り雄琴川の周囲を歩いていたら、暗い農道の菜園の角を曲がったところで足元どころか周囲に沢山の何かの気配。
お、何だ?とライトを向けてみたら、「タヌキの群れ」でした。
ざっと10匹ほどのタヌキが菜園で食事中のところを私が邪魔したようですw
この辺りに住んで20年余りの間犬猫鳥以外に見たのは、イタチ、ヌートリア、亀くらいだったんですけど、車がバンバン通る国道から100メートルも離れていないところで「タヌキの群れ」ですよ。
タヌキがそういうところで飯食ってるというのは、彼らにとってその地域はそれなりに平和ということでしょうか。
私は月に1回のペースで京大前の眼科に通っています。検査の都合で車で行けないことが4か月に1回はあります。
そういう場合電車で行くわけですが、往路は自宅近くの駅から湖西線で山科まで、山科から地下鉄で東山まで、そこからは歩きで20分ほどかけて歩いていきます。
診察は大体土曜日が多いので、復路は同じルートをたどらず、三条通、河原町通、新京極、四条通、烏丸通等をたどって京都駅までぶらぶらと歩いていきます。
このコロナ過でそういう場へ出かけることもなくなったので、街並みを楽しんで帰ってくることにしています。
1月だったか、右目の手術前の検査の帰りに東本願寺の前で気がつきました。
これは東本願寺流のジョークなのか、それとも大真面目に書いただけなのか。
想像してみてください。
プーチンとゼレンスキーがお互い拝みあってるところをw
私は信仰心など持ち合わせていませんが、戦争やってるより、拝みあってる方がましな世界だと思えます。
どういう世界がいいですか?
94615 20220706 1010
94767 20220713 0840
![]()
紛れる
2022年6月16日(木)
以前も書いたと思うんですけど、私腰痛持ちです。
腰痛持ちと言っても何時も痛いわけじゃなくて、理学療法士らしからぬ或いは患者らしからぬ体の使い方の時に痛みが出るわけで、常日頃は注意深くしていれば何の支障もありません。
それでも年のせいか6、7年前から左足の裏が痺れるようになってきました。
ここ半年は右足の裏も痺れるようになってきています。
先日風呂に入っていて足の裏を洗っている時に気付いたんですが、両足ともに「魚の目」が出来ていましたorz
ま、それだけの話なんですけどね。
94272 20220616 0910
94336 20220620 1005